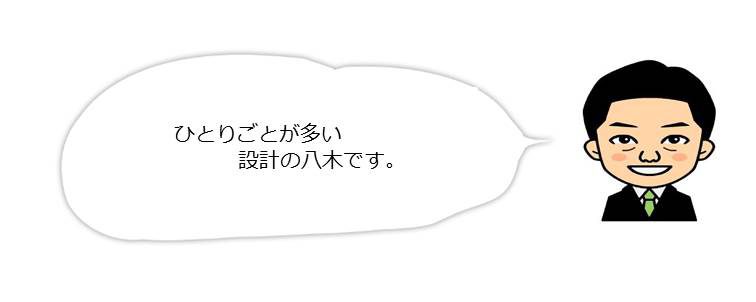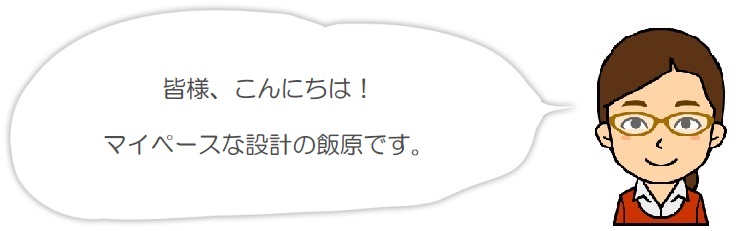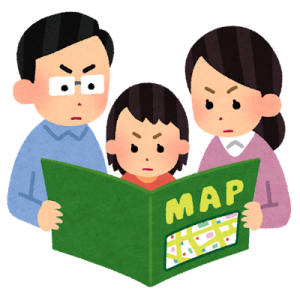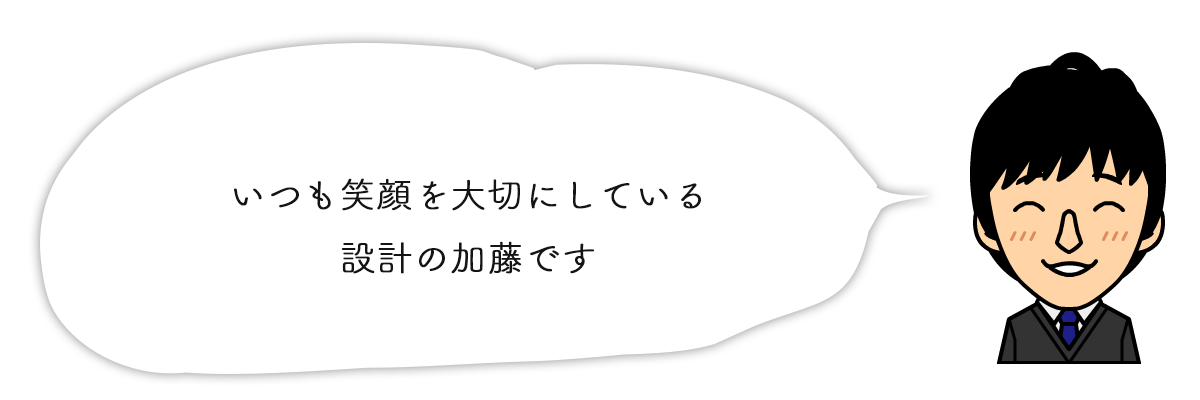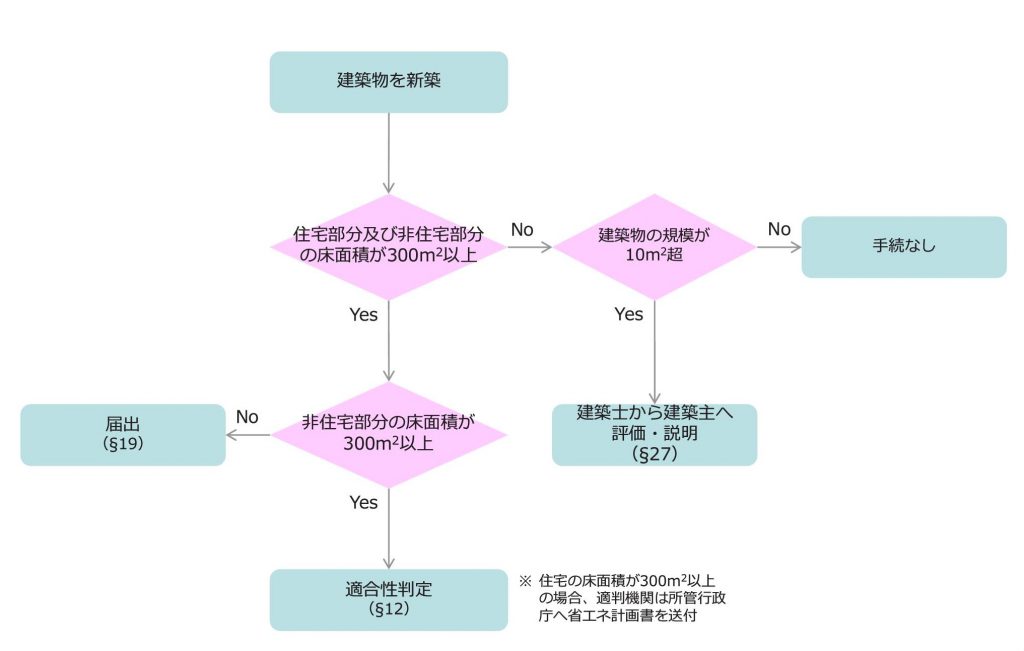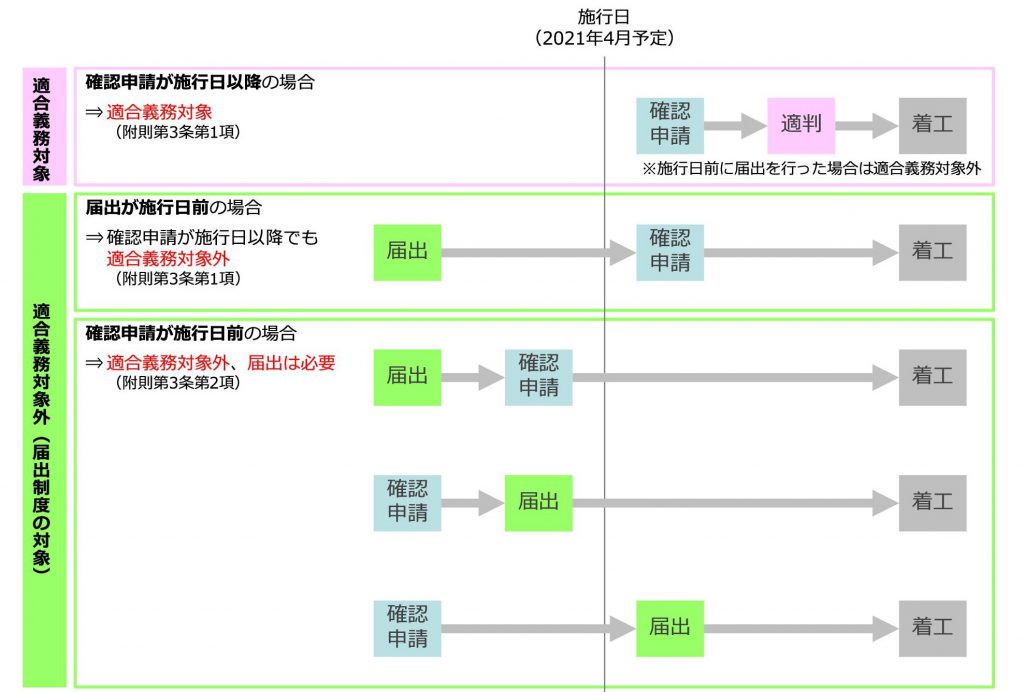こんにちは、暑い日が続きますが、突然激しい雨が降ったりと天気の急変が多くなっているように感じます。
日本は自然災害が多い国であり、最近でも静岡県熱海市で起きた令和3年7月伊豆山土砂災害での土石流よる被害が記憶に新しいところかと思います。
亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げるともに、被災地の一日も早い復興を願うばかりではありますが、こういった土石流の可能性がある場所は熱海だけに限らず、全国に約66万カ所あると言われています。
今、お住まいの地域や働いていらっしゃる地域がどんな地域なのか知ることで、いざというときのために平時から必要な備えをすることができ、防災、減災に繋がっていきます。
そのために本日はご自身の身の回りの地域がどういった災害のリスクがあるのか調べることができる、”ハザードマップ”の調べ方についてご紹介したいと思います。
”ハザードマップ”とは自然災害の発生した際に、危険が発生すると思われる個所や避難場所などをまとめた防災・減災のためにつくられた地図です。
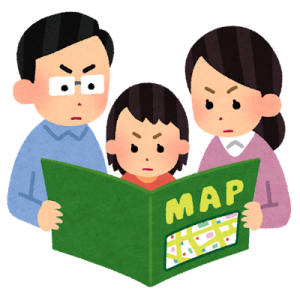
地域にどんなハザードマップがあるのか調べたい際には国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」がおすすめです。
「ハザードマップポータルサイト」 https://disaportal.gsi.go.jp/
ハザードマップポータルサイトでは”重ねるハザードマップ”と”わがまちハザードマップ”を見ることができます。
1. 重ねるハザードマップ
災害リスク情報や防災に役立つ情報を、全国どこでも重ねて閲覧できるマップです。
”場所を入力”から調べたい市町村を入力し、災害種別から調べたい災害を選ぶことでマップ上にエリアが表示されます。災害種別は洪水、土砂災害、津波などに分かれており、それらをすべて重ねて自身の地域にどんな災害リスクがあるか調べることができます。
2. わがまちハザードマップ
市町村が作成したハザードマップを見つけやすくまとめたリンク集です。
”まちを選ぶ”から調べたい市町村を選択することで、その市町村が発表しているハザードマップのHPへ飛ぶことができます。
市町村によってはハザードマップだけではなく防災ガイドブックなども配布している市町村もありますので、ぜひ確認をしてみてください。
また、インターネットでハザードマップを確認する事はとても便利ではありますが、いざ災害が起きた際にインターネットが繋がらない、アクセス集中により見ることができないと言った可能性があります。そのためネット上だけではなく紙でのハザードマップを入手しておく事も大切です。
それぞれの市町村で公開されているハザードマップを予め印刷して保管しておいたり、お住まいの市区町村役場の窓口で紙でのハザードマップを入手したりすることができます。
一家に一枚は用意をし、いざという時の為の行動をしっかりと確認できるようにしておければと思います。